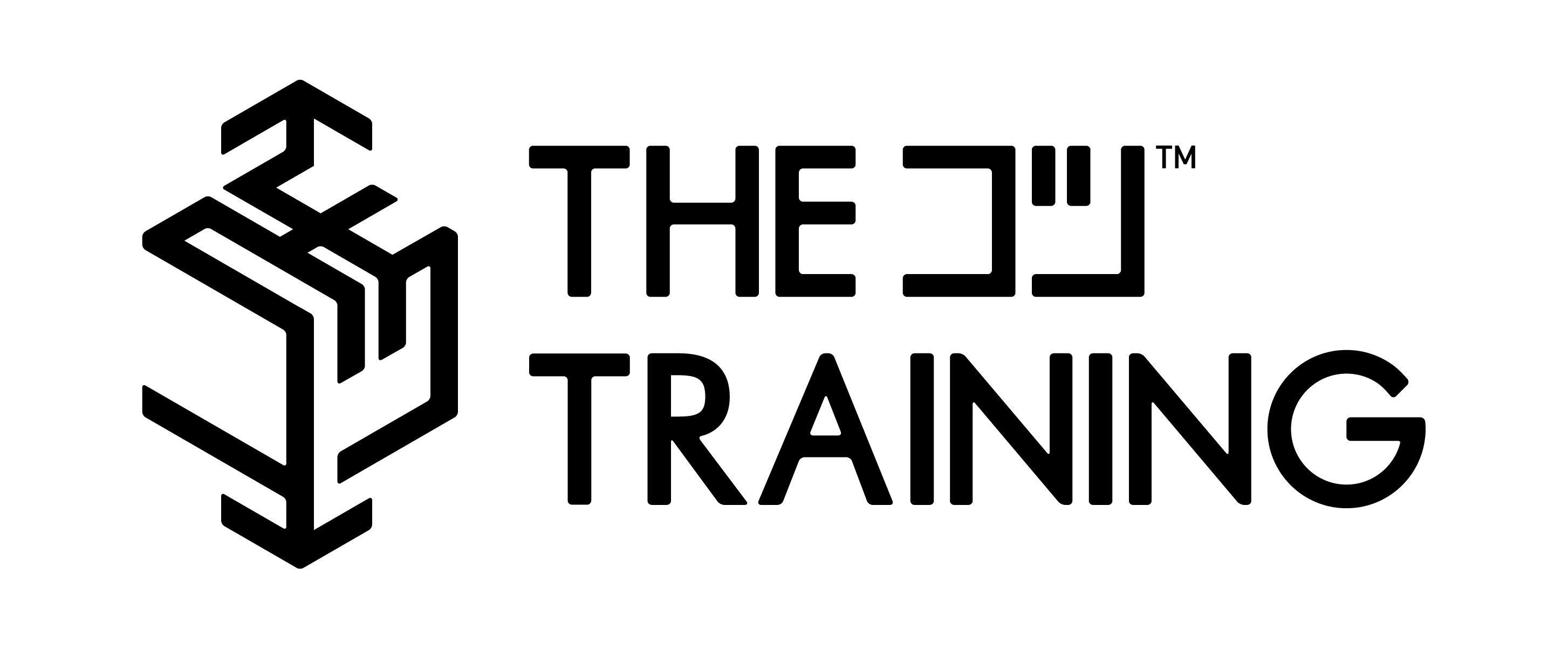古武術でよく使われる『浮身』という言葉。
字面だけ見てみると「浮いている」「身体」ということになりそうですが、この浮いているとはどういうことか?
『抜重』とも何となく似ているような気もしますが何が違うのか?
今回はこれらの違いについて、私なりの解釈を加えつつ、その浮身を身につけるためのステップトレーニングをご紹介します。
『浮身』とは姿勢なのか?
浮身の状態を作るために、まず「浮身の姿勢を作る」ということがなされる場合がありますが、古武術を扱った書籍を読む中で感じる『浮身』とは、どうも形ありきのものでは無いように思います。
「脚はこうで、重心はこうで…はい出来上がり。」とはいきません。浮身に「形(カタ)」のようなものはなく、剣術の中でも「居合い」や「立って構えている」ときもそれぞれ浮身をかけるという表現がなされます。となると、ある特定の状態だけ切り取ってこれが浮身だというよりも、あらゆる姿勢、動きの中で浮身を使いこなせることに意味があると考えた方が良さそうです。
そもそも超能力者でもない限り、我々ヒトが宙に浮いた状態で居続けることはまず不可能なわけですが、瞬間的であれば宙に浮くことは誰でも可能です。
この「いつでも瞬間的に宙に浮いたような状態を作れる姿勢・動き」を『浮身』とここでは定義します。
すると『浮身』とは古武術の中だけで使われる掴みどころのないような言葉ではなくなり、日常から競技レベルまでヒトのあらゆる動作の中でいつでも使えるものへと変わっていきます。
歩いている最中ですらも、瞬間的に浮身をかけることは可能です。いついかなるとき刀で斬られるか分からないような状況での身体捌きと考えれば、当たり前と言えば当たり前ですね。
『浮身』と『抜重』の違いとは?
『抜重』も落下するタイミングで一瞬身体が宙に浮きますが、これと『浮身』はどう違うのでしょうか?
『抜重』は
「瞬間的に身体の支えを外すこと」、
『浮身』は
「いつでも抜重できる構えのこと」。
抜重は「動作」を指し、
浮身は「抜重に至るための身体の状態」を指す。
そのように考えると、それぞれが別個のものではなく、切り取り方が異なるだけで両者併存しているものと理解できます。
浮身の対極にある『居着き』
『居着く』という言葉も、古武術の世界でよく使われる印象ですが、この『居着く』とは「地面に踏み込んだ脚に体重がかかりすぎて、足が地面から離せないような状態」をいいます。つまり、すぐに次の動作に移ることが難しく、その場から離れられずとどまってしまう、居続けてしまうような踏み込み方のことです。
この『居着き』は古武術の中でも忌み嫌われる状態です。何故なら戦いの場面においては、その場から動けなくなった状態では容易に刀で斬られてしまうからです。
『浮身』の作り方
関節がこれ以上動かない、身体の支えが外せないところで、抜重をかけることは非常に難しいため、浮身を作るには、常に抜重可能な余白が必要です。
この「余白を残しながら動く」というところが大きなポイントです。
どっしりと安定させすぎた構えでは、浮身となることは難しく、また身体中に力が入りすぎていると瞬時に動き出すことが難しくなるため不必要な筋収縮は排除する、すなわち脱力できていることも重要なポイントです。
浮身を作るためのポイントは、
①動きの余白を持つこと
②脱力できていること
③いつでも抜重がかけられること
④居着かないこと
の4つです。
この4つをベースにいついかなる場面でも瞬時に動き出すことができていれば、それは『浮身』を使いこなせていると考えて良いのではないでしょうか?
『抜重』が理解できていない場合は、以下の記事から抜重がどういうものか頭と身体で理解するところから始めましょう。
浮身を利用したステップトレーニング
では実際に浮身を使いこなせているときの動きとはどのようなものなのか?
どんな動きで、どんな感覚の動きとなるのか実際に確認しながら体感してみましょう。
Unweighting Steps Ⅰ ( open / cross )



Unweighting Steps Ⅱ ( side / forward )



※ 【Unweighting Steps Ⅰ / Ⅱ [浮身ステップ 1•2]- Full ver. -】の動画視聴料はそれぞれ【¥330(税込)】となります。
動画視聴をご希望の方は、THE コツ™️ TOOLs オンラインショップから¥330分の動画視聴チケットをご購入ください。(両方を視聴希望の方は¥660となります。)
ご記入くださったメールアドレスへ動画視聴可能なURLをお送りします。
カラダ Design Lab.®︎
代表 堤 和也